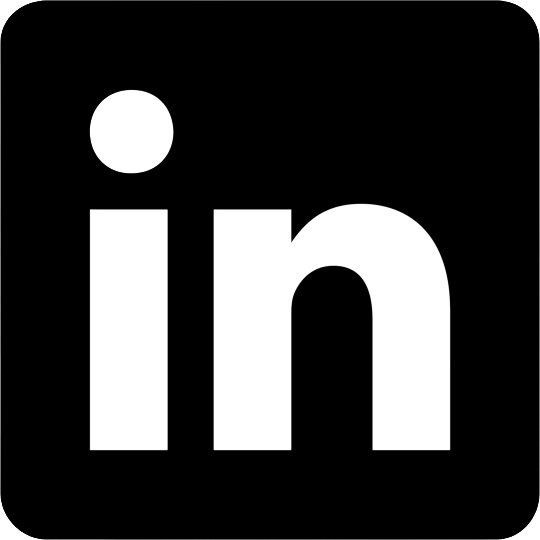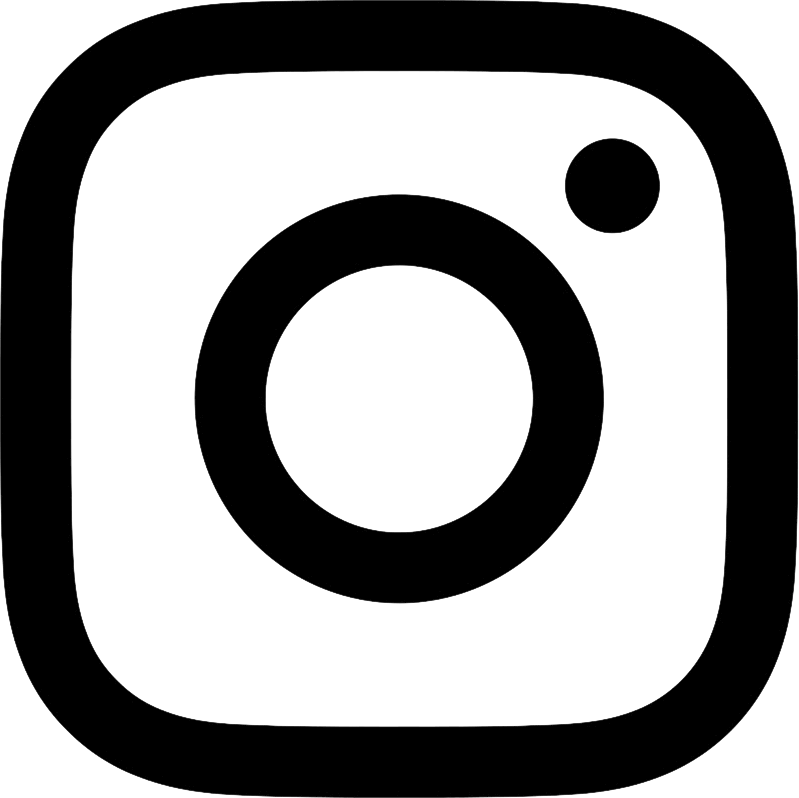佐藤 祥 著
2025年10月31日
日本の文化的影響力はかつてないほど高まっている。記録的なインバウンド観光、世界的な日本食レストランのブーム、そして日本の工芸とデザインへの持続的な関心。しかし、日本企業や創業者が獲得する価値は、この注目度に遥かに及ばない。これは製品の問題ではない。コミュニケーションの問題なのだ。
恵まれた国内市場では、共通の文脈があるため、品質そのものが「語る」ことができた。長年にわたり、世界をリードする経済大国である日本では、企業はこの環境の中で安定した経営を享受してきた。しかし、日本経済が低迷し、かつては選択肢だった海外展開が必要不可欠となる中で、企業の間にギャップが生まれた。海外では、馴染みのある文脈が消失する。多様性の上に築かれた市場は、機能だけでなく、価値観や哲学の明示的なコミュニケーションを求める。自分の取り組みがなぜ重要なのかを言語化できなければ、プレミアム価格を設定できない。コモディティになってしまうのだ。
これが日本企業が適応できなかった現実である。共通の美意識や文化的コードが浸透した国内市場に慣れていたため、彼らはストーリーや意味で競争することを学ぶ機会がなかった。その能力がなければ、「手頃な価格で高品質」という哲学は、低マージンのコモディティ競争に陥る自己実現的な罠となってしまう。
「これが日本企業が適応できなかった現実である。共通の美意識や文化的コードが浸透した国内市場に慣れていたため、彼らはストーリーや意味で競争することを学ぶ機会がなかった。」
他国はこのことを早くから学んでいた。イタリアやフランスがグローバル市場で競争する必要に迫られたとき、彼らは価値を伝えるための体系的な仕組みを構築した。単なる「Made in Italy」といった法的保護だけでなく、ラグジュアリーブランドを統一したストーリーのもとにまとめるComité Colbertのような調整機関も整備した。さらに、デザイナー、シェフ、職人たちを教育し、単に何を作るかではなく、なぜそれが重要なのか、所有することが何を意味するのかを言語化できるようにしている。
イタリアンレザーやフランスワインがプレミアム価格を実現できるのはそのためだ。テロワール、伝統、サヴォワール・フェールについての何十年にもわたる体系的なストーリーテリング。その基盤となるインフラ(用語集、起源についてのストーリー、訓練されたアンバサダーなど)が、工芸を価格決定力へと変換する。日本には並外れた工芸があるが、このようなインフラはほとんど存在しない。
ソニーやトヨタのような大企業は、何十年もの高額な失敗を通してこれを学んだ。しかし、日本企業の95%は中小企業である。彼らにはこのフレームワークがない。製品も、工芸も、ストーリーもある。しかし、それらを誠実に国際的に伝えるシステムがないのだ。
「ソニーやトヨタのような大企業は、何十年もの高額な失敗を通してこれを学んだ。」
これこそがK&Cの構築するものだ。日本企業が、日本らしさを損なうことなく、グローバル市場が理解できる言葉で価値を言語化できるコミュニケーション・インフラである。
最も根本的なレベルで、日本企業は三つの問いに答える必要がある:
なぜ存在するのか。
なぜ重要なのか。
なぜ人々は耳を傾けるべきなのか。
これらの答えは、企業が自らの取り組みを伝えるすべての場面に体系的に組み込まれなければならない。この仕組みこそがインフラである。日本企業が何を作るかを変えるためではなく、世界に向けて「これまでずっと作ってきたものの価値」を正しく理解してもらうためのインフラだ。
挑戦
この緊急性は仮説ではない。このインフラがない年月、日本企業は、単により良いストーリーを語る競合他社に対し、何十億もの価値を放棄してきた。一方、日本の人口動態の崖は、国内専一戦略への回帰が不可能であることを意味する。“機会”の窓は閉じつつある。
しかし、この状況がこれまでと異なるのは次の点にある—日本文化への世界的関心が史上最高であるということ。需要は存在する。製品も存在する。欠けているのは架け橋、つまり日本の卓越性を、真の価値が伝わる視覚・文章・体験の言語に体系的に翻訳する力だ。
これは日本らしさを失うことではない。むしろ、世界に日本の魅力を真正面から届けるということだ。グローバルに日本であること。
それが、K&Cの仕事である。
1
Brand Finance、グローバルソフトパワーインデックス2025:プレスリリース(2025年2月25日)、日本が全体で4位、ビジネス・貿易で1位を確認。
2
ロイター、2025年4月17日:日本は2024年に記録的な3,687万人の訪問者を迎えました。
3
朝日新聞(英語版)、2024年10月25日、MAFF調査:海外の日本料理レストラン20万9,000店、前年比+13%、2017年比+77%。
4
世界銀行国民経済計算データ。日本は1960年代後半から世界第2位の経済大国でしたが、2010年に中国に、2023年に名目GDPでドイツに追い抜かれました。
5
日本の名目GDPは1995年に約5.3兆ドル、2024年に約4.2兆ドル(IMF世界経済見通しデータベース、2024年10月)。
6
OECDデータは、日本の実質賃金が1990年代半ば以降、ほぼ停滞しており、定期的な下落があることを示しています。2023年の実質賃金は、インフレ調整後で1990年代のレベルとほぼ同じでした。
7
OECD平均年間賃金データ(2023年)。日本:PPP調整で約41,000ドル、ドイツ:53,000ドル、米国:77,000ドル。名目数値は異なりますが、同様の相対的なギャップを示しています。
8
国立社会保障・人口問題研究所(日本)、「日本の将来推計人口:2016-2065」(中位出生率変動予測)
佐藤 祥 著
2025年10月31日
日本の文化的影響力はかつてないほど高まっている。記録的なインバウンド観光、世界的な日本食レストランのブーム、そして日本の工芸とデザインへの持続的な関心。しかし、日本企業や創業者が獲得する価値は、この注目度に遥かに及ばない。これは製品の問題ではない。コミュニケーションの問題なのだ。
恵まれた国内市場では、共通の文脈があるため、品質そのものが「語る」ことができた。長年にわたり、世界をリードする経済大国である日本では、企業はこの環境の中で安定した経営を享受してきた。しかし、日本経済が低迷し、かつては選択肢だった海外展開が必要不可欠となる中で、企業の間にギャップが生まれた。海外では、馴染みのある文脈が消失する。多様性の上に築かれた市場は、機能だけでなく、価値観や哲学の明示的なコミュニケーションを求める。自分の取り組みがなぜ重要なのかを言語化できなければ、プレミアム価格を設定できない。コモディティになってしまうのだ。
これが日本企業が適応できなかった現実である。共通の美意識や文化的コードが浸透した国内市場に慣れていたため、彼らはストーリーや意味で競争することを学ぶ機会がなかった。その能力がなければ、「手頃な価格で高品質」という哲学は、低マージンのコモディティ競争に陥る自己実現的な罠となってしまう。
「これが日本企業が適応できなかった現実である。共通の美意識や文化的コードが浸透した国内市場に慣れていたため、彼らはストーリーや意味で競争することを学ぶ機会がなかった。」
他国はこのことを早くから学んでいた。イタリアやフランスがグローバル市場で競争する必要に迫られたとき、彼らは価値を伝えるための体系的な仕組みを構築した。単なる「Made in Italy」といった法的保護だけでなく、ラグジュアリーブランドを統一したストーリーのもとにまとめるComité Colbertのような調整機関も整備した。さらに、デザイナー、シェフ、職人たちを教育し、単に何を作るかではなく、なぜそれが重要なのか、所有することが何を意味するのかを言語化できるようにしている。
イタリアンレザーやフランスワインがプレミアム価格を実現できるのはそのためだ。テロワール、伝統、サヴォワール・フェールについての何十年にもわたる体系的なストーリーテリング。その基盤となるインフラ(用語集、起源についてのストーリー、訓練されたアンバサダーなど)が、工芸を価格決定力へと変換する。日本には並外れた工芸があるが、このようなインフラはほとんど存在しない。
ソニーやトヨタのような大企業は、何十年もの高額な失敗を通してこれを学んだ。しかし、日本企業の95%は中小企業である。彼らにはこのフレームワークがない。製品も、工芸も、ストーリーもある。しかし、それらを誠実に国際的に伝えるシステムがないのだ。
「ソニーやトヨタのような大企業は、何十年もの高額な失敗を通してこれを学んだ。」
これこそがK&Cの構築するものだ。日本企業が、日本らしさを損なうことなく、グローバル市場が理解できる言葉で価値を言語化できるコミュニケーション・インフラである。
最も根本的なレベルで、日本企業は三つの問いに答える必要がある:
なぜ存在するのか。
なぜ重要なのか。
なぜ人々は耳を傾けるべきなのか。
これらの答えは、企業が自らの取り組みを伝えるすべての場面に体系的に組み込まれなければならない。この仕組みこそがインフラである。日本企業が何を作るかを変えるためではなく、世界に向けて「これまでずっと作ってきたものの価値」を正しく理解してもらうためのインフラだ。
挑戦
この緊急性は仮説ではない。このインフラがない年月、日本企業は、単により良いストーリーを語る競合他社に対し、何十億もの価値を放棄してきた。一方、日本の人口動態の崖は、国内専一戦略への回帰が不可能であることを意味する。“機会”の窓は閉じつつある。
しかし、この状況がこれまでと異なるのは次の点にある—日本文化への世界的関心が史上最高であるということ。需要は存在する。製品も存在する。欠けているのは架け橋、つまり日本の卓越性を、真の価値が伝わる視覚・文章・体験の言語に体系的に翻訳する力だ。
これは日本らしさを失うことではない。むしろ、世界に日本の魅力を真正面から届けるということだ。グローバルに日本であること。
それが、K&Cの仕事である。
1
Brand Finance、グローバルソフトパワーインデックス2025:プレスリリース(2025年2月25日)、日本が全体で4位、ビジネス・貿易で1位を確認。
2
ロイター、2025年4月17日:日本は2024年に記録的な3,687万人の訪問者を迎えました。
3
朝日新聞(英語版)、2024年10月25日、MAFF調査:海外の日本料理レストラン20万9,000店、前年比+13%、2017年比+77%。
4
世界銀行国民経済計算データ。日本は1960年代後半から世界第2位の経済大国でしたが、2010年に中国に、2023年に名目GDPでドイツに追い抜かれました。
5
日本の名目GDPは1995年に約5.3兆ドル、2024年に約4.2兆ドル(IMF世界経済見通しデータベース、2024年10月)。
6
OECDデータは、日本の実質賃金が1990年代半ば以降、ほぼ停滞しており、定期的な下落があることを示しています。2023年の実質賃金は、インフレ調整後で1990年代のレベルとほぼ同じでした。
7
OECD平均年間賃金データ(2023年)。日本:PPP調整で約41,000ドル、ドイツ:53,000ドル、米国:77,000ドル。名目数値は異なりますが、同様の相対的なギャップを示しています。
8
国立社会保障・人口問題研究所(日本)、「日本の将来推計人口:2016-2065」(中位出生率変動予測)
Case Studies
Services
Clients & Awards
Portfolio
Approach
Terms and Conditions
Sign up to
receive
the latest news.